 |
 |
 |
| カットされた板どうしの接続に、タボを使う。 ドリルで8mmの穴を開け、木工用ボンドをつけて差し込み、小槌でたたい埋め込む。 |
 |
 |
| とりあえず、よりそっていない幅の狭い方の板(天板)と 縦の板をタボを打って木工用ボンドで固定。 このまま一晩放置して、完全に接着する。 |
 |
| 幅の広い方の板(天板)を片側ずつタボを打って、接着する。 |
 |
| かなりそっているのが分かる。 |
 |
| ひっくり返して反対側も同様に貼り付ける。 そってしまっている板はどうにもならないが、ネジを使ってしめれば、ある程度は修正できる。 天板の中央にあらかじめドリルで穴を開け、ネジをしめる。 |
  |
| ネジの頭が完全に埋まるように、ネジの頭の直径より大きい穴を途中まで開けておく。 ここでは、直径8mmのタボを後で利用できるように、ドリルも8mmを使った。 |
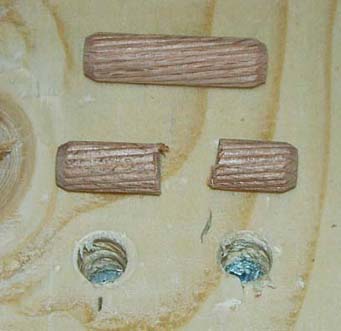 |
| タボをノコギリで切る。 |
 |
| ネジを隠すために穴をタボでふさぐ。 |
 |
| ヤスリをかければ完成♪ |
 |
| このままだと角がとがっているので、 ディスク・グラインダーにサンドペーパーを取り付け、角を落とす。 さらにヤスリをかけ、最後に紙やすりで表面全体をなめらかにする。 次に裏板のかどに、キャスター用の穴をドリルで開ける。 |
 |
  |
| 最後に家具屋でもらった亜麻仁油(アマニユ)を塗って、オイル仕上げを施せば、 出来上がり〜♪ |
 |
BEFORE |
 |
AFTER |
 |

















